【書評】赤井 伸郎・宮錦 三樹 著 『教育の財政構造:経済学からみた費用と財源』
2025.7.2

赤井 伸郎・宮錦 三樹 著
『教育の財政構造:経済学からみた費用と財源』
(慶應義塾大学出版会、2025年)
大学改革支援・学位授与機構 教授
水田健輔
本書は、初等教育から高等教育まで多段階の教育財政について、責任主体(国・地方自治体)別に費用と財源の整理を行っている点で類書にない特徴を有している。対象は国・公立の教育機関に対する直接の財源負担と費用支出であり、制度の詳細に目を配り、執筆時点での最新の情報を網羅するように心がけられている。その目的については、日本の財政が厳しい制約下にある中、効率的効果的な教育政策が実施されるために必要なエビデンスを得る上で、不可欠となる制度情報やヒントとなるデータ分析結果を示すことにある。よって、教育政策の評価を公財政負担と機関支出を含めた視点で行う場合に、まず読まれるべき書籍として推薦したい。
全体は、序章を含めて8章で構成されており、各章の内容には次のような特徴が確認できる。まず序章では、本書で「教育財政学」と呼んでいるものについて、隣接領域との異同を整理し、本書の対象とアプローチ(公共経済学アプローチ)を明らかにしている。そして第1章では、教育振興基本計画の推移を顧みるとともに、客観的なエビデンスにもとづくPDCAサイクルの構築が求められていることを指摘している。その上でPISAのスコアと教育支出の関係を検証し、支出の規模自体がそのまま教育成果につながる訳ではないことを例として示している。つまり、財源の量だけでなく、配分方法や支出構造により着目すべきである点を強調している。次に第2章では、国・地方自治体が責任主体となっている公的教育機関への機関補助について、その制度的な成り立ちと資金の流れが全体像として把握できるようにまとめられている。
続く第3章から第5章は、責任主体別・教育段階別の財源構造について、執筆時点での最新情報がまとめられており、一読すると日本の初等教育から高等教育に至るまでの公財政による機関補助がどのようになされているかを把握できる。まず第3章は、国立大学を対象とした財源構造、特に運営費交付金制度を解説しており、評価制度と業績連動型配分の仕組みを細かく紹介している点に特徴がある。効率的効果的な財源措置を希求する上で、メリハリのある財源配分がどうあるべきかについて検討する基礎情報となる。次に第4章では、公立小中学校を対象としており、国から地方自治体への財源措置と両者の責任分担について、制度の歴史的な変遷を含めて論じられている。特に義務教育費国庫負担金の地方交付税による一般財源化により、給与削減による効率化のインセンティブが働く点についてページを割いている。そして、第5章は公立大学を対象としており、国から地方自治体への地方交付税措置について、制度上の説明がなされている。基準財政需要額への公立大学経費の算入については、先行研究でも学問系統別の単位費用の差と推移がよく取り上げられるが、単位費用×測定単位×補正係数の細かい算出方法まで平易に説明している点に特徴がある。なお、ここでも国と地方自治体の責任分担の在り方について問題提起がなされている。
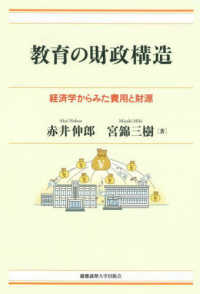 最後に第6章と第7章は、学術論文で仮説検証した内容を一般読者にも理解可能なように加筆し、収録している。まず、第6章については、公立小中学校の消費的支出とその費目内訳について、「規模の経済性」が働いているかどうかを検証している。結論として、支出総額については規模の経済性が働いているが、個別の費目によっては働かないものもあることが示された。少子化の進展とともに、小中学校の統廃合が課題となる中、こうした実証研究の結果を政策立案に活かしていく必要性を示唆している。次に第7章では、公立大学の「規模の経済性」と「範囲の経済性」について検証している。結果として、規模の経済性は、文系教育、理系教育、研究のいずれでも効いており、機関統合等の政策が費用効率の側面から支持されることを明らかにしている。そして、注目すべきは範囲の経済性の検証結果であり、文系教育と理系教育はそれぞれ単体で実施した方が費用効率的であるが、どちらの教育も研究と一体生産した方が範囲の経済性が働くという結論が示されている。この点については、豊富な先行研究も参照しつつ慎重な解釈と取り扱いが必要と思われるが、大学の機能設計を考える上で興味深い知見といえる。
最後に第6章と第7章は、学術論文で仮説検証した内容を一般読者にも理解可能なように加筆し、収録している。まず、第6章については、公立小中学校の消費的支出とその費目内訳について、「規模の経済性」が働いているかどうかを検証している。結論として、支出総額については規模の経済性が働いているが、個別の費目によっては働かないものもあることが示された。少子化の進展とともに、小中学校の統廃合が課題となる中、こうした実証研究の結果を政策立案に活かしていく必要性を示唆している。次に第7章では、公立大学の「規模の経済性」と「範囲の経済性」について検証している。結果として、規模の経済性は、文系教育、理系教育、研究のいずれでも効いており、機関統合等の政策が費用効率の側面から支持されることを明らかにしている。そして、注目すべきは範囲の経済性の検証結果であり、文系教育と理系教育はそれぞれ単体で実施した方が費用効率的であるが、どちらの教育も研究と一体生産した方が範囲の経済性が働くという結論が示されている。この点については、豊富な先行研究も参照しつつ慎重な解釈と取り扱いが必要と思われるが、大学の機能設計を考える上で興味深い知見といえる。
ちなみに、本書には5つの「コラム」が設けられているが、閑話休題的な軽い読み物ではなく、本筋に関わる重要な情報が含まれている。
なお、あとがきで触れているとおり、公平性の議論や私立機関への公財政負担、あるいは就学支援等の個人補助については、今後の研究の進展と本書の内容への発展的反映が待たれるところである。また、丁寧な制度解説が本書の特徴の一つだが、今後の制度変更や政策動向については、読者が情報を補完しながら読むことが求められる。
※この記事は、『IDE 現代の高等教育』(NO.672 2025年7月号(7月1日発行))からの転載です。
