教員紹介:松島法明 教授
2025.7.28

教員紹介:松島法明 教授
2025年4月に着任した松島法明先生にインタビューを行いました。松島先生は産業組織論の理論分析を専門としています。
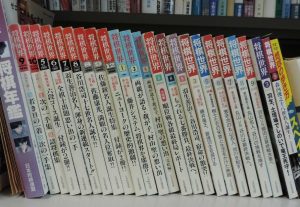
研究室の本棚にある将棋雑誌
研究室の棚に将棋の雑誌を置いているのですね!お好きなのですか。
大学院後期課程のころから将棋が好きでした。特に詰め将棋が好きで、パズルのように論理的に解いていくところに惹かれます。もしかすると、研究の思考と近いものがあるのかもしれません。ある時、研究発表の後に「あなたの説明の仕方は詰め将棋のようだ」と言われたことがありました。「これがこうだからこう」といった論理展開が、将棋の詰め筋と似ているのかもしれませんね。
これまでの研究について紹介していただけますでしょうか。
企業間競争の帰結について、学部生でも理解できる極めて素朴な理論モデルを使って分析してきました。
21世紀初頭は民営化や民業圧迫といった公企業に係る問題があったので、この問題を考えた結果、それなりに引用される成果を出せました。この中の1つでは、公企業の存在が民間企業の投資を過剰に引き出す可能性があり、過剰投資を抑制するために民営化が必要になることを明らかにしています。
企業間取引関係を考慮して企業間競争の問題を考えると従来の考えとは大きく異なる帰結が得られることもわかってきたので、この問題も考えた結果、ぼちぼちの成果を出せました。この中の1つでは、川下企業が取引関係にある川上企業と垂直統合すると、当該企業が製品を競争相手と差別化する程度が高まることを明らかにしています。他にも、現存の川上企業が川下企業との取引を確保するために、この川下企業と排他条件付取引[1]を締結できる市場環境も明らかにしています。
上記の問題を発展させ、企業数が増えて競争が厳しくなると企業利潤が減るといった素朴な常識が成り立たないような競争環境も考えてみました。これも、それなりに引用される成果になりました。例えば、商標価値の低い製品を供給する企業が数多く参入することで、商標価値が高い製品を供給する企業間の競争が緩和される競争環境を明らかにしています。他にも、技術投資が重要な産業において、普通の水準にある企業が参入すると、現存企業の中で技術優位にある企業の利潤を改善する可能性も明らかにしています。
最近は個人情報の活用に関する研究をされていると伺っています。
個人情報に係ることは大学院のとき(20世紀末)から時々考えていました。当時は電子商取引の黎明期で、光通信や携帯電話市場が盛り上がっていました。電子商取引では個人情報や閲覧履歴を追跡できるので、この情報を活かした価格付けができるようになることで、価格競争の様相が変化すると漠然と考えていました。21世紀頭からは別の研究を中心に考えていましたが、最終消費者向けの役務で強い影響力を有する企業が隆盛してきたことを受けて2010年代前半から再び考え始め、意外と引用される成果を出せました。
例えば、企業が2期間競争する下で1期目に供給した顧客について選好の情報が入手できることを利用して、2期目において1期目の顧客に個別価格を提示できる状況を考えました。その結果、製品特性を変更できない場合には1期目の価格付けが非対称になる一方、製品特性を事前に設定できる場合、対称な企業であっても一方の企業だけ差別化の程度を低くすることを明らかにしました。他にも「各企業が個別価格を提示できる場合は競争が促進されやすい」という従来の見解とは大きく異なり、競争環境の下でも個別価格を設定できることで完全に消費者の余剰を搾取する結果が実現しうることを明らかにしています。
個人情報を活用した企業間競争については、これと関連する規制が欧州を中心に導入され、これに反応して経営戦略を変更する有力企業も存在するので、しばらくは研究する必要がある課題になると思いますし、最近、1つ成果を出せました。
どのようなきっかけで研究が始まることが多いですか。
主に2つのアプローチがあります。1つ目は既存モデルの拡張を試みる方法です。現実との対応を意識しなくてもできるという意味で思いつきやすい一方、分析結果と現実世界の対応や示唆を説明しにくいのが難点です。
2つ目は現実の問題を分析する方法です。この方法で分析可能な研究を思いつくのは難しい分、うまくいった場合にはいい論文ができます。また、Management Scienceなど経営学の雑誌に出版する論文はこちらの方が多い気がします。
少し前の話ですが、国立大学に勤務していた際に公務員の給料が民間企業に連動して下がることが望ましいかどうかを疑問に感じたため、分析をしようとしました。ただし、最初は分析がうまくできませんでした。公企業の労働者が賃金を要求しても社会厚生に影響しないので均衡賃金が求まらなくなるからです。研究に詰まって2年後、単純な仮定を置けば解決することに気づきました。公企業の利潤が負になってはいけない、という仮定です。この仮定は当時の郵便局の状況とも整合的で、自然な仮定でした。利潤に仮定を置くことで制約条件付きの最大化問題を解けるようになり、論文になりました。
現実から研究が生まれるきっかけとして、私はanecdotal evidence[2]をとても大切にしています。例えば、これまでの研究の紹介の際に「素朴な常識が成り立たないような競争環境」について考えたと申し上げた企業参入についての論文は、大企業が小企業の参入を競争相手と思わない、むしろ歓迎するというanecdotal evidenceが直感的には奇妙だという話を共著者と話して、モデル化できそうだったことが論文につながりました。
大学院生を指導するにあたって心掛けていることについて教えてください。
経済学は基礎知識の習得を非常に重要視します。もちろん、私も全く気にしないわけではありません。しかし、それ以上に研究課題や問いをいかに分析可能な形に設定するかが非常に難しいです。学生のそのような能力を涵養すべく、可能な限りの手助けを行っています。
まずは学生から何か分析したいアイディアを持ってきてほしいと思っています。その際、基本的に突っぱねずになぜそのテーマ・課題が面白いと思ったのか聞くことにしています。その面白さがモデル分析の際に手助けとなります。また、どのようなジャーナルに出版可能な研究になりうるか、という主観的な見通しも伝えるようにしています。
とはいえ、博士後期課程の学生にはタイミングを見計らって、見通しがある程度たっている共著を持ち掛けたほうが良いと判断すれば、そうすることもあります。これまで博士後期課程で指導した学生は標準修業年数内で修了・就職をされる学生が多かったですが、これは結果論なところもあります。
産業組織論の魅力や面白いところはどんなところですか。
現実の企業間競争の帰結の背後にある論理が理論分析によって明快に理解できることだと思います。背後の論理に応じて注力すべき活動がわかるようになると思います。
私自身、公正取引委員会の競争政策研究センターで所長を務めています。ここでは、公正取引委員会の職員に経済学の理解を深めてもらうことが主な仕事です。研究センター主催のシンポジウムでコメントしたり、職員から相談を受けた際に産業組織論をはじめとする学術的知見を提供したりしています。経済学の博士号を持つ職員もいるため、そうした知見は最終的に政策形成の現場で活用されています。
とはいえ、最終的に制度設計を決めるのは法制度なので、経済学はあくまで補助的な役割にとどまります。ただ、その補助的な役割が果たす意義は非常に大きいと感じています。
松島先生の研究については以下のページでも紹介されていますので是非ご覧ください。先生曰く「1つ目のブログは論文が受理されるごとに更新する予定です。」とのことです。
https://nmatsush.blog.shinobi.jp/
https://sdgs.osaka-u.ac.jp/research/3142.html
*****
教授 松島法明(まつしまのりあき)
研究テーマ: 情報通信技術の進展を踏まえた企業間競争の理論分析
専門分野:応用ミクロ経済学(産業組織、競争政策、経営の経済分析)
学位:博士(工学)
<代表的な業績>
Choe, C., N. Matsushima, S. Shekhar, 2024. The bright side of the GDPR: Welfare-improving privacy management. Management Science, Forthcoming.
Lu, Q., N. Matsushima, 2024. Personalized pricing when consumers can purchase multiple items. Journal of Industrial Economics 72 (4), 1507-1524.
Choe, C., S. King, N. Matsushima, 2018. Pricing with cookies: Behavior-based price discrimination and spatial competition. Management Science 64(12), 5669-5687
<現在取り組まれている研究プロジェクト>
個人情報に係る規制が企業間競争に与える影響
個人情報を活用した価格差別が企業間競争に与える影響
労働市場や投入物市場などの川上市場と最終財市場(川下市場)の相互依存関係を考慮した企業間競争
<個人ホームページ>
<好きな論文>
Anderson and Renault (2006) Advertising Content, American Economic Review
序文だけで理論分析の結果と直観が理解できる書き方になっている上に、問題設定の重要性も非常によく説明できているので、勉強になります。
(博士後期課程 辻本篤輝)
[1] 他の川上企業と取引しない約束
[2] 逸話や風聞など、定性的な情報に基づいた証拠

岐阜県白川郷にて(2022年末)
