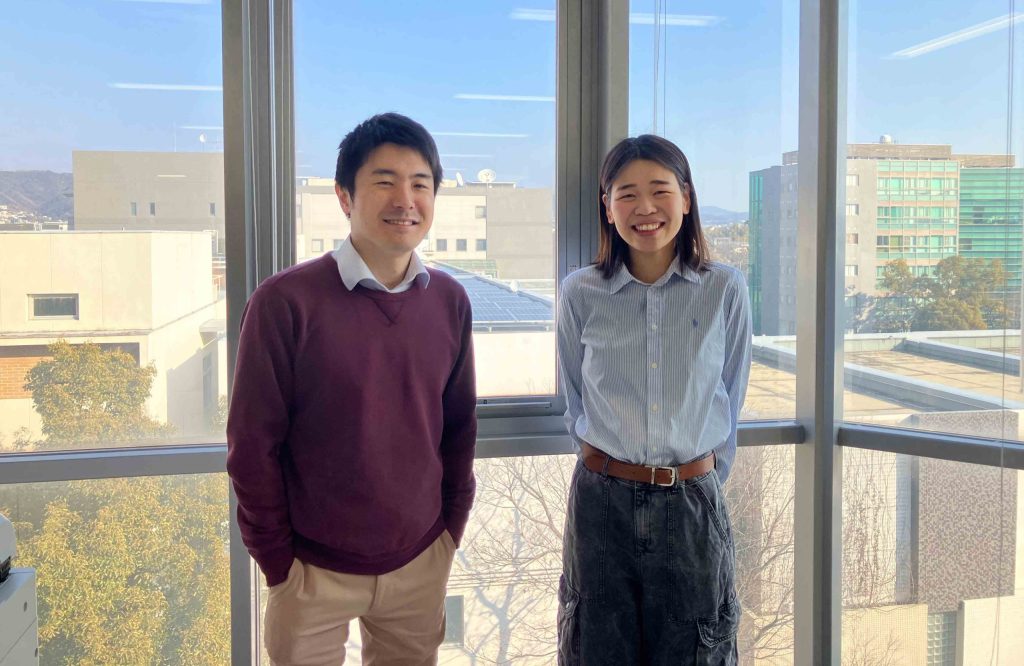南和志先生『People’s Diplomacy: How Americans and Chinese Transformed US-China Relations during the Cold War』出版・大阪大学賞受賞インタビュー
2025.1.23
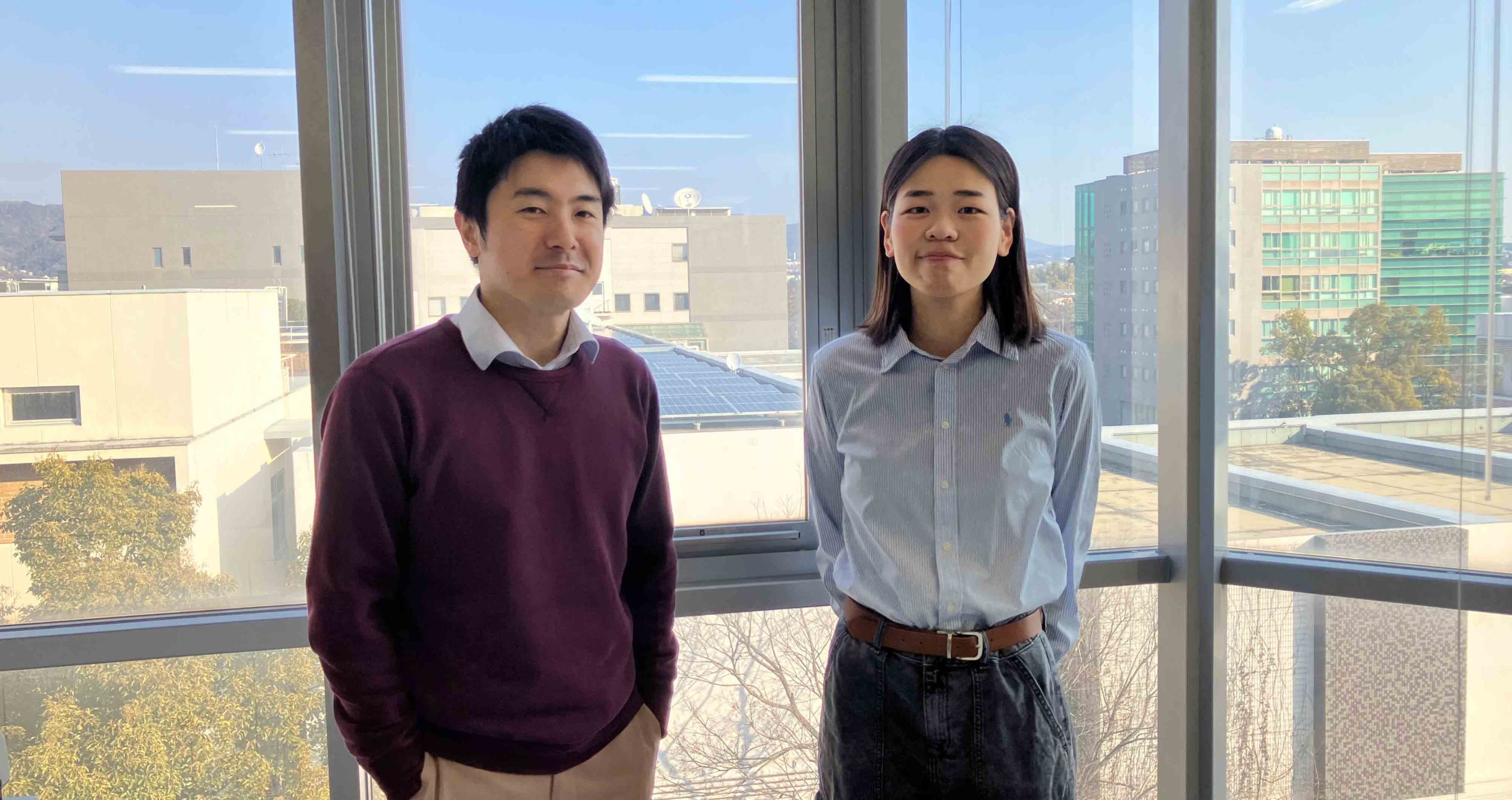
南和志先生 出版・受賞記念インタビュー
2024年3月に著書『People’s Diplomacy: How Americans and Chinese Transformed US-China Relations during the Cold War』を出版し、同年12月には大阪大学賞を受賞した南和志准教授にインタビューを行いました。
(写真左側:南先生・右側:筆者)
著書『People’s Diplomacy: How Americans and Chinese Transformed US-China Relations during the Cold War』の内容についてお聞かせください。
冷戦期の米中関係について、特に1970年代「米中和解」のプロセスを分析したものです。従来、米中和解といえば1972年2月のニクソン訪中など、両国の政策決定者に焦点を当てるものが多かったのですが、本書は幅広い米国人・中国人に分析対象を広げ、米中関係が敵対から協調に変化した過程を包括的に描き出しています。具体的には、両国の企業家、科学者、学生、ジャーナリスト、アスリート、音楽家など政府関係者ではない人々が、どのように米中関係を再構築したのかを論じています。昨今、米中対立が激化する中、米国の対中「エンゲージメント(関与)」が失敗であったという論調が目立ちますが、本書では、そもそも「エンゲージメント」は米国政府の政策ではなく、米中国民の主導で形成された思想なのだと結論づけています。また、本書の特徴として、米国だけではなく、中国の一次史料も網羅的に使用していることが挙げられます。その中には、残念ながら現在は様々な理由からアクセスできなくなってしまった史料も多く含まれています。本書では、政府関係者ではない非国家アクターに着目していることで、伝統的な外交史では捉えられてこなかった広義な国際関係を分析しています。
歴史系の研究は長期間かかり、忍耐強く取り組む必要がある印象を持っているのですが、研究のスケジュールの組み方など、特に大事にされていることはありますか。
確かに、歴史系の研究は成果が出るまで時間を要する場合が多いので、のんびりしているといつの間にか時間ばかり経ってしまいます。研究のスケジュールに関しては、私は特に秘策があるということはなく、毎日できる限り読んで、書いて、いつの間にか終わっているという場合が多いです。強いて言うなら、研究成果に関して短期目標に固執しすぎてしまうと研究の柔軟性が失われる恐れがあるため、ある程度余裕を持ちながら、中・長期の目標を意識するようにしています。
今取り組まれている研究や今後の研究の展望についてお聞かせください。

現在は、戦後東アジア全体を対象に、石油外交に関する研究を進めています。「東アジアの奇跡」とも称される同地域の急速な経済成長は、1950年代のエネルギー革命により燃料の主役に躍り出た石油に依存していましたが、石油資源に乏しい東アジア諸国は、供給源確保のため、東西冷戦の垣根を超えた競争・協調を展開しました。石油資源をめぐる外交交渉、石油開発のための技術協力、海外プロジェクトにおける政治家・商社・銀行の相互依存関係を調査することで、石油が戦後東アジアの国際関係に絶大な影響を与えたことを明らかにしたいと考えています。
研究中の困難はどのようなものがありますか。
研究に必要な資料を集めることが困難になってきています。私の研究で使用する資料は現在の政情が不安定な地域を対象としている場合もあり、予算制約がありながらどれだけ柔軟な発想をしてクリエイティブな方法で問題を解決するか、ということが求められています。そのため、都度試行錯誤しながら研究を進めています。
政治学の研究をするうえで必要な心構えはありますか。
歴史研究の観点から考えると、最も大事な力は基本的な読み書きの能力だと思います。歴史研究は入り口は広いですが、読み書きの能力や、大量の情報を処理・分析して争点・論点を絞る能力が必要です。また量の面でいうと本を何百冊と読む必要があり、次には読む人がいることを意識しながら、伝えたいことがきちんと伝わるよう緻密に検討しつつ文章を書く能力を磨くことと、それを成し遂げる強い意思が必要です。歴史研究を志している学生さんにはぜひ上記の点を踏まえた上でがんばってほしいと思います。
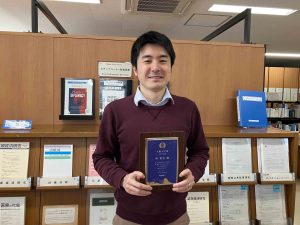
この度は大阪大学賞の受賞、おめでとうございます。
ご感想をお聞かせください。
非常に光栄です。(くらいしか言えません笑)
大阪大学HP:令和6年度大阪大学賞表彰式を開催
OSIPP公式HP:令和6年度大阪大学賞若手教員部門 受賞
先生のお話を聞いて
研究活動には忍耐力と実行力が不可欠であることを改めて実感しました。先生から資料収集の方法について伺い、世界情勢に左右される難しさや、時間と思考を駆使して取り組んでいる姿勢を知り、歴史研究の困難さを改めて感じました。筆者もデータ収集活動で苦労することが多いのですが、まだまだアプローチする方法やできることの可能性について考える余地があることを認識しました。また、研究アイデアは頭の中だけに留めず、他者に伝えて進めることの重要性についても教えていただきました。この姿勢は、分野を問わず研究活動において共通する重要な考え方だと思います。
(OSIPP博士前期課程 奥野愛理)